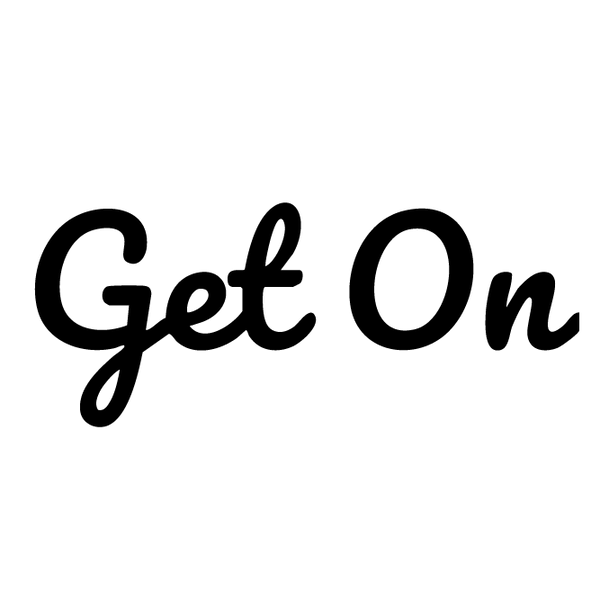服のライフサイクルを考えるという新しい視点
私たちは洋服を「買う」ことに意識を集中しがちですが、その後のライフサイクルについては見過ごされがちです。生産から廃棄に至るまで、服は大量の資源とエネルギーを消費しています。実はこのライフサイクルを理解することが、環境負荷を大幅に軽減する第一歩となるのです。
日本における服の廃棄の現状
日本では年間およそ50万トン以上の衣料品が廃棄されているといわれています。そのうちリサイクルやリユースされる割合はまだ低く、多くが焼却処分されています。この背景には、リサイクルインフラの不足や消費者の情報不足が挙げられます。
POINT 不要な服をただゴミとして捨てるのではなく、「再利用」「寄付」「資源化」という選択肢を持つことがエシカル消費につながります。
服を長持ちさせるためのケア術
ライフサイクルの前半部分において重要なのは「長く着る」ことです。洗濯ネットの活用、低温洗濯、天然素材専用の洗剤使用など、少しの工夫で衣類寿命を延ばすことができます。また、定期的なメンテナンス(ほつれ修理、毛玉取りなど)も衣服の延命につながります。
リユース市場と新サービス
近年では「服の手放し方」に革命が起きています。メルカリやラクマなどのフリマアプリに加え、ブランド公式のリユースサービスも急増。たとえばパタゴニアは「Worn Wear」プロジェクトを通じて、服の修理や中古品を再販売し、資源の有効活用を推進しています。
POINT 公式リユースサービスを活用することで、正規の保証や品質チェックが受けられ、安心して次のユーザーへ届けられます。
海外ブランドのライフサイクル戦略
欧米では、ZARAやH&Mが自社回収ボックスを設置し、古着を新しい繊維原料として再利用しています。IKEAも衣料部門に進出し、古布を家具用素材に転用する試みを行っています。こうした海外事例は、日本の消費者にとっても参考になります。
寄付・社会貢献につながる手放し方
着なくなった服を福祉団体や海外支援団体に寄付することも有効です。ユニクロは「リサイクルBOX」を店舗に設置し、難民や被災地に衣類を寄付する仕組みを確立しています。
失敗しやすい服の処分法と注意点
注意したいのは、自治体による資源回収ルールの違いです。混合素材の衣服を可燃ゴミとして処分すると、結果的に環境負荷が増大します。また、「なんとなく捨てる」は最も避けるべき選択肢です。
POINT 「手放す前に、使える手段が他にないか?」を考える習慣を持つだけで、エシカルな行動が実現します。
まとめ
服のライフサイクルを見直すことはただの片付けではなく、環境と社会への責任ある行動です。リユースやリサイクルの選択肢を知ることで、ファッションはより持続可能で意味のあるものに変わります。