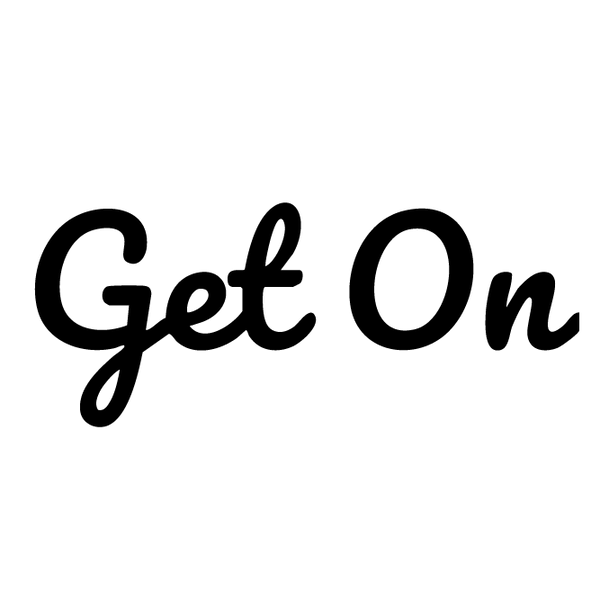UGCが導く、サステナブルブランドの未来戦略とは?共創型エシカル消費の新潮流
Share
近年、サステナブルブランドの成長は消費者の倫理意識の高まりと連動して加速しています。しかし、広告に対する信頼が揺らぐ中、企業が信頼を得るために新たに注目しているのが「UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)」です。これは、単なる口コミではなく、消費者とブランドが対等に共創する新しいブランド価値の構築手段とも言えるでしょう。
なぜUGCがサステナブルブランドに適しているのか
サステナブルブランドは、商品の品質や価格だけでなく、その背後にあるストーリーや理念、環境・社会への配慮といった“見えにくい価値”に支えられています。こうした価値は、企業自らが発信しても受け手に「プロモーション」と見なされがちです。しかし、UGCを通して消費者自身の言葉や体験が語られることで、より深い信頼が生まれます。
POINT UGCは、サステナブルブランドが持つ「理念先行」のイメージを、生活者視点に引き寄せることで“日常的な選択”に変換する装置となる。
広告離れとエシカル消費の一致
とりわけZ世代・ミレニアル世代においては、ブランドからの一方的なメッセージよりも、共感可能な生活者の視点に強く影響される傾向があります。さらに、従来のSNS広告やインフルエンサー施策に対しても「広告臭が強い」と警戒する動きが強まる中、UGCは非広告的でオーセンティックな情報源として再評価されています。
POINT エシカル消費に積極的な若年層ほど、ブランドの「語り口」よりも「語られ方」に敏感になっている。
UGCによる「共創」こそがブランドの強さ
サステナブルブランドにとって、UGCは単なる証言ではなく、“共創”の証明でもあります。例えば、廃棄物を用いた再生プロダクトに関して、ユーザーが制作背景やアレンジを投稿することで、そのブランドの「循環性」がユーザーの生活と結びつくのです。
このように、UGCはブランドの理念を押しつけるのではなく、「共感される文脈」に再構築する役割を担っています。ある意味で、消費者が自らサステナビリティの旗を掲げ、その一員として参加していると感じられる仕掛けとも言えるでしょう。

UGC戦略に成功したサステナブルブランド事例
たとえばアメリカのアウトドアブランド「Patagonia」は、製品のリペアやリユースに関するUGCキャンペーンを積極的に展開しています。消費者が長年着用しているジャケットの修繕記録や、子どもに受け継いだエピソードなどをSNSで発信することで、「製品寿命=ブランド価値」を実感させる流れを作り出しました。
日本では「People Tree」や「Ethical&SEA」なども、購入者によるコーディネート投稿をブランド公式で再シェアすることで、“共に社会を良くする仲間”という文脈を強化しています。
ブランド主導から、ユーザー起点のエンゲージメントへ
従来のブランディングでは、「企業が設計した世界観にユーザーを引き込む」スタイルが主流でした。しかし、UGCを重視するブランドは、その逆の構図を取ります。「ユーザーが発信するリアルな物語」をブランドが支援し、文脈を照らし出すことにより、より強い信頼と関係性が築かれるのです。
このとき重要になるのは、単なるシェアやリポストにとどまらず、UGCそのものに価値を与え、ブランドの世界観に取り込む姿勢です。
POINT ブランドはUGCを「素材」として受け取るのではなく、「共同制作者」としてのリスペクトを持って扱う必要がある。
これからのUGCは“プロダクト・アウト”ではなく“カルチャー・イン”
UGC活用の未来は、単なるプロダクトの説明や口コミを超えて、ライフスタイルや価値観そのものの共有へと向かっています。特にサステナブルブランドにおいては、生活者一人ひとりが「選択を通じて社会とつながる」という感覚を持つことが、継続的なエンゲージメントの鍵となります。
たとえば、リサイクル素材の使用を誇るよりも、「この服を着て、誰かがゴミを減らした」と感じられるようなUGCが拡がれば、消費行動は単なる購買ではなく、参加型の文化体験へと進化していくでしょう。
UGC戦略は 単なるプロモーションではなく、“共創される文化”としての役割を持ち始めている。
効果的なUGC戦略のためのポイント
- 投稿のハードルを下げる(ハッシュタグ設計、リワード制度など)
- 共感を得やすいテーマを設ける(環境貢献、ストーリー性)
- 自社の理念やSDGsとの接点を明確にする
- UGCを一時的な話題ではなく、ブランドDNAに統合する
そして最も重要なのは、「投稿者との対話」を忘れないこと。コメントやリシェアだけでなく、フィードバックやイベント招待などを通じて、UGCに“意味と価値”を付与していくことが信頼形成の鍵になります。
共創型ブランディングにおいて UGCは単なる“拡散手段”ではなく、“持続可能な関係性を築くメディア”と捉えるべきである。